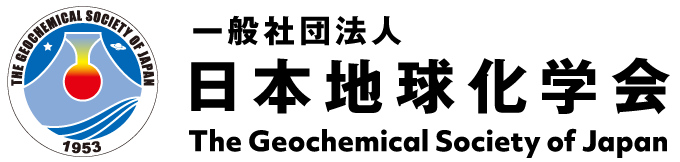2025年9月
東京科学大学
理学院地球惑星科学系
横山 哲也

日本地球化学会会長就任にあたり、会員の皆様にご挨拶申し上げます。
本会の発足は、前身である地球化学研究会が誕生した1953年にまでさかのぼります。10年後の1963年には現在の名称「日本地球化学会」となり、学会の強固な基盤が築かれました。さらに2017年には法人化し、一般社団法人日本地球化学会として新たな一歩を踏み出しました。70年以上の歴史を有する学会の会長を務めることは大変光栄であると同時に、その責任の重さを痛感しており、背筋が伸びる思いです。会員の皆様のご期待に応えられるよう、2年間全力で取り組む所存です。
先日の役員選挙に際しては、会長候補として所信を述べました。その所信をもとに、ここで改めて、今後の学会運営に関する私の考えをお伝えいたします。
第一に、誰もが参加しやすく、魅力ある学会を目指します。
2024年9月、金沢大学での年会夜間集会では、会員数減少や若手の地球化学離れについて活発な意見交換が行われました。その議論を通じ、世代を問わず多くの研究者がさまざまな活動に意欲的であることを改めて実感しました。第一線の研究者が地球化学の魅力を積極的に発信し、それが若手へと波及する―そうした好循環を継続できるよう努めてまいります。
第二に、会員サービスのさらなる充実を図ります。
和文誌の郵送、研究集会参加費の優遇、各賞の授与制度などが特典として提供されていますが、より身近に実感できるサービスを整備したいと考えています。たとえば、リニューアルされた学会ウェブサイトの会員限定公開動画をさらに充実させ、楽しんでいただける情報を発信する所存です。また、歴史ある和文誌「地球化学」を、会員を惹きつけ続ける魅力ある雑誌として維持・発展させてまいります。
第三に、若手研究者の育成に注力します。
地球化学会の若手研究者のモチベーションは非常に高く、つながりを求める声も数多く寄せられています。こうした中、2024年初頭に若手会の活動が再開され、2025年3月には信州大学で若手会が開催されました。2026年3月には名古屋大学での若手会開催も予定されています。次代を担う人材の成長に資するこのような活動を、今後も積極的に支援してまいります。
最後に、国際化を一層推進し、学会の国際的な存在感を高めます。
中国・韓国・台湾との合同国際シンポジウムの経験を活かし、東アジアにおけるネットワークの拡充を図ります。また、Goldschmidt国際会議を通じてGeochemical Society(GS)やEuropean Association of Geochemistry(EAG)との連携も強化してまいります。5月の所信ではお伝えすることができませんでしたが、幸い、2028年7月にGoldschmidt国際会議が東京で開催されることが正式に決まりました。2003年倉敷大会、2016年横浜大会に続き、12年ぶり3度目の日本開催となります。日本地球化学会は主催団体であるGeochemical Societyと協定を締結し、LOCとして東京大会の運営に参画します。今後2年間はこの準備にあたる重要な時期であり、戦略的な取組みが求められます。東京大会は日本の地球化学コミュニティの存在感を国際的に高める絶好の機会であり、セッション提案、関連分野との連携、独自性あるワークショップ開催など、多様な可能性があります。その実現には若手からベテランまで幅広い会員の皆様のお力添えが不可欠です。何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
日本地球化学会が、すべての会員にとって「居心地の良い場」となるよう、誠心誠意努めてまいります。今後ともご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。