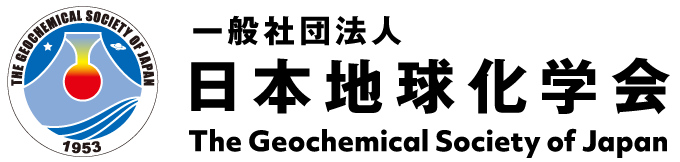|
■広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻 表層環境地球化学研究室 光延 聖
第4回目の「院生による研究室紹介」は広島大学大学院 博士課程後期2年の光延(みつのぶ)が担当させていただきます。広島大学の地球惑星システム学専攻には地球化学系の研究室として同位体地球惑星科学研究室(日高洋 教授、寺田健太郎 助教授)と表層環境地球化学研究室があります。今回は私が所属しています表層環境地球化学研究室を紹介いたします。 表層環境地球化学研究室のメンバーは、清水洋 教授と高橋嘉夫 助教授の2名のスタッフと博士研究員1名、大学院生9名、学部生4名の総勢16名(2006年10月現在)で構成されています。少し前までは構成員の女性の割合が高かったのですが、最近ではめっきり減ってたくましい研究室になってしまいました。 |
 |
 では具体的に最近どのようなことについて研究を進めているのかについて紹介します。研究室のテーマは多岐にわたっているので簡単に説明するのは難しいですが、まず、大きなテーマとしてX線吸収分光法の1つであるXAFS法による固相中の微量元素のスペシエーションが挙げられます。XAFSは、ある特定の元素に着目し、その元素のまわりの構造や、どういう化学状態にあるかを調べる方法です。これを使って酸化還元環境の変動に伴って価数および動態が変化するヒ素、アンチモン、セレンなどの有害元素の化学状態と溶出-吸着機構の関係について研究を行なっています。また、エアロゾル中のイオウの存在状態や酸性雨の原因となる硫酸のエアロゾル中での中和機構などを観察しています。これまでの研究からエアルゾル中のイオウは硫酸塩で存在しており、また季節や粒径によってエアロゾル中の硫酸塩の種類が変化することがin situに観察されています。(さらに最近の研究から黄砂期試料と非黄砂期試料の比較から、エアロゾルが硫酸を中和する能力が黄砂期には高まることがわかってきています。)さらには、時間分解XAFS法を用いた固液界面の化学反応解析や高感度な蛍光分光XAFS法を用いた極微量元素のスペシエーションなど、通常のXAFS法を発展させた手法の開発も行っています。 次に、天然有機物質の1つで微量元素の環境動態に大きな影響を与えている腐植物質やバクテリア表面との希土類元素(REE)や環境ホルモン物質の相互作用についても研究しています。REEの存在状態によって多様に変化するREEパターンの形状を使って様々な官能基をもつ腐植物質やバクテリアのどんなサイトとどのような構造を持ち結合しているのかを考察しています。これらの室内実験結果を天然試料にトレースしREEパターンを海水中でのREEの結合サイト推定や、バクテリア生成鉱物の指標として応用できることがわかってきています。 また、放射性トレーサーを用いた天然模擬実験により、地球表層での微量元素の移行挙動を支配する種々の因子について研究を進めています。特に岩石間隙水中での元素の拡散現象や錯生成時の元素の拡散挙動に対して応用し新しい知見を得ています。また、基礎的な地球化学的プロセスが未解明なレニウム(Re)、オスミウム(Os)についても放射性トレーサーを利用し、海洋での固液分配に関する研究を行なっています。ReおよびOsの地球化学的挙動はRe-Os壊変系への応用など地球化学的に非常に重要であり、得られた知見は近々に発表予定です。というふうに、いくつか研究室で現在進めている研究テーマについてトピック的に紹介しましたが、非常に多岐にわたる研究を進めていることがわかっていただけたかと思います。これらの研究のひとつひとつを深く掘り下げて質の高い研究を行なうことがこれからの大きな目標です。 他に研究室全体の活動として週に一回、セミナーで個々の研究進捗状況の発表や関連する論文の紹介等を行っています。セミナーでは毎回様々な研究分野の話が聞けるので非常に新鮮です。一方で、理解するのにも一苦労なのですが(笑)、自身の研究のヒントになることも少なくなく、視野を広げることにも役立っています。また、興味を持った分野について知識を深める少人数形式の自主ゼミも随時立ち上がっています。 |
 |
 |
| 追伸ですが、来年は日本地球化学若手会が広島で開催されます。地球化学をこよなく愛する若手のみなさん!是非こぞってご参加ください。広島で美味しいお好み焼きでもほおばりながら将来の地球化学・環境化学について語り合いましょう!それでは、失礼いたします。光延でした。 |
広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻 表層環境地球化学研究室
2006年12月21日