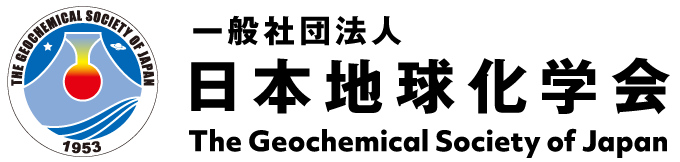|
■海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター 地球古環境変動研究プログラム 地球化学グループ 柏山祐一郎
今回は、独立行政法人海洋研究開発機構・地球内部変動研究センター・地球古環境変動研究プログラム・地球化学研究グループ(50字、長い!)の紹介です。あまりに長くて我々もつい失念してしまうのですが、略称で「JAMSTEC・IFREE4の地球化学研究グループ」と覚えてくだされば幸いです。 |
 |
 まずは、「元素分析計・連続フロー・同位体質量分析計(EA/MS)」システム。自慢はその「世界一の感度」です。当グループの小川奈々子さんがここ数年来心血を注いで改造や微調整に取り組んできた装置です。最近ついに、窒素量で150ナノグラム、炭素量で500ナノグラムの試料があれば、窒素・炭素の安定同位体組成を0.2パーミル以下の分析精度で測定することができる、という状態まで到達しました。これは、市販品に比べて数百倍の分析感度をもち、堆積物試料などから単離される微量の有機化合物についても,いとも簡単に同位体分析ができるようになりました。実は、さらに微量な試料で分析ができるよう、マニアックな改造を試みているようです(写真2)。 |
 |
|
さて、これらの強力な「武器」を駆使した最近の研究をいくつかご紹介しましょう。まずは、クロロ色素や化石ポルフィリンと呼ばれる化合物の研究です。クロロ色素は、クロロフィルなど光合成生物が持つ緑色の色素ですが、化石ポルフィリンというのは、そのクロロ色素が堆積物中に保存され、続成作用を経て変化した赤色の色素です。これら化合物は光合成生物の同位体情報を保存していて、分子レベルでの同位体組成を調べることで、現在・過去の光合成プロセスに関する生理や生態、ひいては海洋表層の環境情報を引き出すことができます。特に、これらは窒素を含む化合物なので、過去の光合成活動に関連した窒素循環を復元しうる希有なツールです。このツールを白亜紀の海洋無酸素事変に堆積した「黒色頁岩」に応用した結果は、窒素固定を行うシアノバクテリアが重要な一次生産者であったことを示しました。また、京都大学生態学研究センターと共同で近代以降の琵琶湖における物質循環の研究や,氷期における日本海の古環境復元,さらにマサチューセッツ工科大学と共同で先カンブリア代の古環境復元にも成果を挙げつつあります。今後,統合国際深海底掘削計画という場で,温室地球・白亜紀の地球表層環境の総合的な理解へ向けて,このツールを武器に切り込んでいく予定です。
次は、アミノ酸の分子レベル窒素同位体組成を用いた生態学指標の開発と応用です。当グループでは、各種アミノ酸の化合物レベルの窒素同位体組成を、簡便な前処理とGC/C/IRMSにより測定する手法を確立しました。そして、生物の組織を構成する必須アミノ酸と非必須アミノ酸の窒素同位体比の差が、その捕食段階に対応して系統的かつ定量的に変化することを明らかにしました。これは、従来のバルク試料の窒素同位体分析に代わる、食物網解析の解明に非常に有効なツールになりうるものです。私たちは,地質時代の様々な生態系の構造を理解するツールとして捉え、目下いくつかの応用研究を実施中です。 |
 最近は,高野淑識さんが新たに来られ,アミノ酸の立体異性体レベルの窒素同位体測定法の確立という成果を早速出されただけでなく,地殻内微生物活動をモニターする化合物の探索をJAMSTEC内の微生物グループと共同で行っています。近い将来,深海底掘削船「ちきゅう」で採取される堆積物コアに応用され,「生命の下限」に迫ることでしょう。 当グループでは、近々、ホームページを開設する予定で、もっと詳しい研究の様子が知りたい!という方がいらしたら、そのうちホームページの方を覗いてみてください(
|
海洋研究開発機構 地球内部変動研究センター 地球古環境変動研究プログラム 地球化学グループ
2008年1月8日